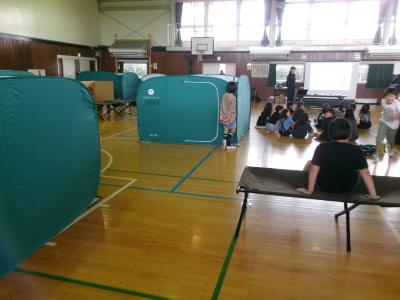学校ブログ
学校ブログ
 走り高跳び
走り高跳び
今日の1時間目、6年生は校庭で体育をしていました。今日はさわやかな気候の1日で外で運動するにはとても
良かったです。6年生なので、用具の準備・片づけとも協力してできていて、素晴らしかったです。
 読み聞かせ
読み聞かせ
今日の朝の活動は読み聞かせがありました。1年生は音楽室に集まり、学年で
お話を聞きました。はらぺこあおむしの大型絵本のお話を聞くときは、知って
いる子は歌を一緒に歌いました。おはなし日和のみなさま、ありがとうござい
ました。
 宿泊体験教室3
宿泊体験教室3
2日目は、散歩、体操、そして、朝食のサンドウィッチ作りです。そのあと、校庭で前の夜つくったペットボト
ルロケットを飛ばしました。この2日間、うまくいったこと、うまくいかなかったことを体験し、いろいろなこ
と学べました。おやじ会の皆様、お手伝いいただいた方々、大変ありがとうございました。
 宿泊体験教室2
宿泊体験教室2
夕食はカレー作りをしました。また、カレーのご飯はお湯で作れるアルファ米でした。おなかいっぱい食べられ
ました。そのあと、花火、肝試し、工作教室などして過ごしました。
 宿泊体験教室
宿泊体験教室
9月20日(土)21日(日)、おやじ会主催の宿泊体験教室がありました。4~6年生の44名が参加しました。
1日目は防災出前講座を受けたり、段ボールベッドの組み立てをしたりしました。ドラム缶風呂にも入りました。
吉川市立北谷小学校
〒342-0036
埼玉県吉川市高富857
TEL.048-982-5158
FAX.048-984-5273
【学校教育目標】
よく考える子
仲良く助け合う子
元気で明るい子
お知らせ
令和6年度学校評価
学校運営協議会議事録(簡易版)
home&school欠席連絡
マニュアルダウンロード