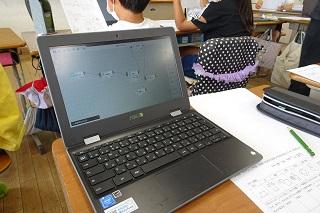学校ブログ
ディジタル・シチズンシップ授業を行いました
今日は、とても暑い日でした。WBGTを常に監視して、その結果、昼休みの外遊びを中止にしました。子供たちにとっては残念だったと思いますが、熱中症は本人に自覚がないところで急に気分が悪くなったり、熱が出たりするので、やむを得ないところです。週末は最高気温が少し下がるようですが、くれぐれもご家族の熱中症防止にご配意ください。
本日、5年生と中学年を対象に、「ディジタル・シチズンシップ教育」を行いました。講師はいつもお越しくださる吉川市教委 教育指導支援員 大西 幸雄 先生です。複数の教室で同時に授業を行うため、大西先生は会議室からリモートで講義を行ってくださいます。
子供たちは大西先生のお話を、モニター越しにしっかりした態度で聞きます。大西先生からも、子供たちの様子はよくみえています。
今回の講義の内容は、SNS上の情報の取り扱い等でした。大西先生が示された資料をもとに、子供たちは話し合ったり、じっくり考えたりして、意見をまとめていきます。ご覧のように、たくさんの子がしっかりした答えをワークシートに意欲的に書き込んでいました。
大西先生の講義は、教えるのを最小限に留め、結論も求めません。そうすることで、子供たち自身の「納得解」を引き出すのです。常に「どうするのがいいと思う?」と子供の考えを尊重します。教えすぎは子供たち自身の考えを深めることにはならないからです。指導者として、最新で魅力的な教材を提供し、子供たちの話し合いを活性化することで、教育の効果を上げていらっしゃいます。
何より、ICTの長所も短所も理解し、正しく活用することで自らの生活を豊かにする子、社会のよき参画者となる資質と能力をもつ子の育成に重点をおいていらっしゃいます。チャットGPTにしても、あれこれ危惧して敬遠するより、「まずは使ってみましょうよ!楽しいから。」というのが大西先生の一貫した姿勢です。
吉川市の子供たちも教職員も、こうしたご指導を継続的に行っていただくことで、ICTの「食わず嫌い」がほとんどないように感じます。そして、「あっ、こうして使うといいじゃん!」というアイディアを協働して考え、よりよい答えをみつけていく。そうした好循環ができていることをはっきり感じます。
到来するsociety5.0。その豊かさを享受し、自らの生活を向上させていくことは自己実現と幸福につながります。吉川市の子供たちは、本当に幸せだなあと思います。大西先生、ご指導をありがとうございました。
音楽 合奏練習 いいですね!
今日も暑かったです!ネット上のWBGT指数とにらめっこでした。「危険」レベルには上がらなかったものの、油断しないで子供達が熱中症にならないよう気を付けていきたいと思います。
5年生が、合奏練習をしていました。今日はパート練習で、全体での音合わせには居合わせなかったものの、すごく真剣で、楽しそうな雰囲気が伝わってきました。
織田先生の指導のもと、テンポよく、リズミカルに練習が進んでいました。中には、リズムに合わせて踊っている子も。いいですね!リズムを身体で刻むって、音楽を楽しむ基本の一つです。
やっぱり、合奏はいい。合唱も素晴しく楽しいのですが、高学年になってくると声を出すことをためらいがちになる子もいます。無理もありません、それも成長過程です。でも合奏なら、気兼ねなく音が出せます。学級の雰囲気がよいと、「音間違い」も笑って許せるのがいい。音楽室は明るいムードに包まれていました。
昨日、プログラミング学習をやらせていただいて、すごく楽しかったのですが、この合奏も「楽しそうでいいなあ」です。自分が奏でた音と、他の楽器の音がばっちり合わさって、曲が完成する。これが合奏の楽しさです。
これこそ、みんなで音楽を学ぶ喜びですね。リモートも便利でいいけれど、やっぱりみんなが音楽室に集まるのが一番だと思います。
4年生 プログラミング学習を行いました
昨日より、最高気温はちょっと低かったようですが、蒸し暑さは相変わらずです。学校では、常にWBGT(熱中症指数)の監視を続け、子供たちに注意喚起しています。おうちでも、着脱できる服装等にご配意ください。
プログラミング教育。学校に課せられた新しい課題の一つです。子供たちがICTを有効活用して、自らの生活を豊かにしたり、ICT社会の望ましい参加者になるための学習です。
今日、4年生の教室をお借りして、私(校長)が主担当で授業を行いました。教材は、吉川市教育委員会からお借りしたSONYのMESHというセンサーです。MESHはとても優れた教材で、「ボタン」「LED」「動き」「人感」「明るさ」「温度・湿度」等からなり、クロームブック上のアプリで簡単なプログラムを組むことができます。
「はい、じゃあ今日はSONYのMESHというセンサーを使ってプログラミング学習を行います。SONYって、知ってる?プレステとかつくっている日本有数のメーカーだよ。」
「あー知ってるー!!」
早速、MESHをクロームブック上のアプリで接続します。「MESHをクロームブックとブルートゥースで接続します。みんなブルートゥースって、知ってる?」
「あー知ってるー!!」「けっこう簡単そう。」
やり方を覚えた子供たちは、さっそくMESHの接続に挑戦します。少し時間がかかりましたが、次々に成功しました。「やったーつながったー!」そして、センサーの動きを試しました。例えば、「ボタン」と「LED」を接続すると、ボタンを押すとLEDが点灯します。また「動き」とクロームブックのスピーカーを接続すると、動きセンサーを軽く振ると、スピーカーから警報音が流れるようになります。子供たちから、「おー!」と歓声が上がります。
「よーしみんな、よくがんばったー。もっと時間をあげたいけど、すまないがここまでー。」
「えー、もっとやりたいですー!」
「ごめんごめん。でもこの授業は、ここからが本番なんだ。このセンサー類を使って、生活に役立つプログラムを考えてもらいます。例えば『プリン泥棒防止装置』!おうちの人から、「宿題終わったら冷蔵庫のプリン食べていいよ」といわれました。でもそのプリンを弟が狙っています。そこで冷蔵庫の扉に「動きセンサー」を貼り付けておきます。そしてクロームブックのスピーカーと接続して、弟が冷蔵庫を開けようとしたら、センサーがプリンのピンチを教えてくれるわけ!どう?生活に役立つでしょう。」
「アハハハー!」「おもしろーい!!」
「そう、じゃ、みんなで生活に役立つプログラムを考えてみよー!」「わーい!!」
子供たちは自分で考えたり、話し合ったりしていろいろなプログラムを考えていきました。部屋の窓から朝日が差し込んだら、『起きなさーい!』という音声が流れる目覚まし時計。気温が30度以上になると、「水分を摂りましょう。」と教えてくれる熱中症防止センサー。おうちに帰ると、明るさを感知して「おかえりなさい、お疲れさまー」といってくれる思いやりセンサー。いやー、どれも素晴らしいアイディアでした。子供の発想の柔軟さに驚かされるばかりでした。
おりしも文科省からchatGPT使用に関するガイドラインが発出されました。その主なねらいは、ICTを正しく活用して、自らの生活を豊かにしたり、新しいアイディアを創造するための有益な資料にしたりすることです。
でも、大人が心配するより、物心がついたことからICTに慣れ親しんでいる子供たちは、紙や鉛筆のように、ずっと自然にICTを便利に、そして有益に使いこなしていくかもしれません。今日の子供たちの様子をみて、そんな希望をもつことができました。
このMESHを使った授業、今後も校内で広げていく予定です。未来を担う、よりよいICTの使い手の育成を目指して。
さ~さ~の~は~ さ~らさら~♪ 各教室の七夕飾り
今日もとても暑かったのですが、昨晩のうちに雨が降ったので昨日よりはいくぶん気温が下がったかな?という感じでしたが、やっぱり暑かったです。
今週金曜日はいよいよ七夕まつり。学校用務員の山崎さんが、各学級に笹の木を配ってくれました。子供たちはさっそく、短冊に願いを書き込んでいました。
1年生の教室では、先生が子供たちの書いた短冊を飾り付けていました。きれいですねえ♡
子供たちも、一生懸命短冊に願いを書いていました。
「棚機(たなばた)」とは、古い日本の禊ぎ行事で、乙女が着物を織って棚にそなえ、神さまを迎えて秋の豊作を祈り人々のけがれをはらうというものでした。そのため、願いは織姫の機織りにちなみ、「技能向上」を願うものとされています。そのため、「おかねもちになりたい」はちょっとちがいます(笑)。誰ですか、「switchのソフトがほしい」とか書いているのは。サンタさんへのお願いじゃないってば。
子供たちもそこのところをきちんと理解していて、「スイミングでもっと泳ぎたい」とか、「テストで100点とりたい」と純粋な願いを書いていました。よしよし。一人の子が、「身長が120センチ以上伸びるように」と書いていたので理由を聞いたら、「前に行ったジェットコースターに身長制限で乗れなかったから、次は乗りたいんだ。だから、120センチ以上に伸びたい。」といっていました。なんて純粋なお願いでしょう。思わずほろり、としてしまいました。大丈夫、きっとかなうよ。
子供たちの短冊の願いをのせて、7月7日はよく晴れますように。そして織姫様と彦星様の、年に一度の逢瀬がかないますように。
国語研究授業 文学教材を読み解く楽しさ
今日も猛烈な暑さとなりました。でも、今のところ熱中症で体調を崩す児童が出ていないのは、ご家庭でお子さんの体調管理をしっかりしていただいていることが大きいと思います。どうもありがとうございます。
本日、2年1組と3年2組で国語の研究授業を行いました。研究テーマは、「読む力の向上」です。本校児童は、県の学力状況調査等から、「読む力」が県平均より低い傾向にあります。そこで、国語科を中心に、子供たちの読む力が向上するよう指導法の改善に取り組んでいます。
2年1組は「スイミー」の授業です。元気をなくしたスイミーが、海で見かける楽しいもの・美しいものに触れ、元気を取り戻す場面の様子をじっくり読みこみました。虹色のゼリーみたいなクラゲ、ブルドーザーみたいなイセエビ、頭をみるころは尻尾をみたことをわすれるぐらい長ーいうなぎ・・・。その幻想的で美しい場面を読み取り、豊かに想像して話し合いました。
読み取った自分のイメージを絵や言葉で表し、黒板に貼って、スイミーを囲む海のすてきな生き物たちの場面を学級全体で再現してみました。子供たちはよく意見を出し合い、考えを深め、物語世界に浸ることができました。
3年2組は、「まいごのかぎ」です。主人公の「りいこ」が、ふとしたことで手に入れたかぎが、不思議な世界に誘ってくれる幻想的な物語です。物語の冒頭、一生懸命描いた図工の絵を友達に笑われたことで自信をなくしたりいこは、まいごのかぎの持ち主を探している間に不思議な光景をたくさん触れて、徐々に笑顔を取り戻していきます。
りいこの気持ちがどのように変化していくか、叙述に基づいて丁寧に読み取っていきました。
子供たちはりいこの心情の変化を示す記述を読み取り、それをもとに意見を交換して、学級全体で考えを共有しました。感心したのは、各自がワークシートに自分の考えをしっかり書けたことです。これは日ごろから意識して練習しないと身に付かない力で、ふだんのがんばりを感じることができました。
「スイミー」も「まいごのかぎ」も、子供たちの眼前に美しいイメージを広げ、想像力を掻き立ててくれる魅力的な文学教材です。授業で身に付けた物語を読み味わう力を、夏休みの読書にもいかしてほしいと思います。
冒頭、「読む力の低下」と申し上げましたが、本校児童に限ったことではありません。読解力の低下は、全国的な傾向です。いえ、わたしたち大人も読む力が低下していないでしょうか。主たる原因は、ネット動画の普及等により、ふだんから文字に慣れ親しむ機会が減少しているからだと思います。
それでも、読む力は、すべての学習の基盤となる非常に大切な能力です。北谷小では授業研究を通じて、子供たちの読む力を高めていきたいと考えます。
吉川市立北谷小学校
〒342-0036
埼玉県吉川市高富857
TEL.048-982-5158
FAX.048-984-5273
【学校教育目標】
よく考える子
仲良く助け合う子
元気で明るい子
令和6年度学校評価
学校運営協議会議事録(簡易版)
home&school欠席連絡
マニュアルダウンロード